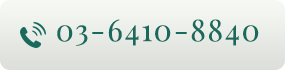皮膚感染症について
 ウイルス、真菌、バクテリア、寄生虫などを原因として引き起こされる皮膚の疾患を皮膚感染症と言います。主な症状は赤みやかゆみ、発疹、びらん(皮膚表面が剥離すること)、腫れ等で、痛みが伴うケースもあります。これらの症状はウイルスや真菌、バクテリア、寄生虫等が皮膚に侵入、増殖することで引き起こされます。肌と肌の直接の接触、感染した物の共有、空気中の微生物による感染など感染経路は様々です。多くの場合、医師の診断と処方薬が必要になります。適切な手洗いや皮膚の清潔を保つこと、傷口の清潔と適切な保護による予防が大切です。
ウイルス、真菌、バクテリア、寄生虫などを原因として引き起こされる皮膚の疾患を皮膚感染症と言います。主な症状は赤みやかゆみ、発疹、びらん(皮膚表面が剥離すること)、腫れ等で、痛みが伴うケースもあります。これらの症状はウイルスや真菌、バクテリア、寄生虫等が皮膚に侵入、増殖することで引き起こされます。肌と肌の直接の接触、感染した物の共有、空気中の微生物による感染など感染経路は様々です。多くの場合、医師の診断と処方薬が必要になります。適切な手洗いや皮膚の清潔を保つこと、傷口の清潔と適切な保護による予防が大切です。
細菌性皮膚感染症
毛包炎(毛嚢炎)について
毛穴の奥の毛根を包んでいる部分を「毛包」と呼びます。この毛包の浅い層に黄色ブドウ球菌等が感染して起こる細菌感染症を毛包炎(毛嚢炎)と言います。原因菌は主に黄色ブドウ球菌ですが、緑膿菌やその他の菌の場合もあります。毛包炎の一種として特によく知られているのは、おできと呼ばれるものです。
毛包炎になると、毛穴のある位置の中央に丘疹と呼ばれる皮膚の盛り上がりができます。この丘疹は膿を持ち、広がって周辺にも白色もしくは赤色に腫れた膿を持つ発疹(膿疱)ができます。「せつ(おでき)」はこの膿疱が硬くしこりになり、ズキズキと痛みを伴うようになったもののことで、特に顔の中心部にできた場合は「めんちょう」と言います。「せつ」は強い痛みや圧迫感、熱感を伴います。毛包炎では、軽度のうずくような痛みとかゆみ、刺激感などが症状として挙げられ、全身どこにでも現れますが特に顔や首の後ろ、太もも、臀部(お尻)、陰部周辺などによくみられます。
毛包炎(毛嚢炎)の治療
毛包炎では、数が少ない場合は患部を清潔にすることと抗菌薬の外用で治療をします。「せつ」や「よう」のようになっているケースでは、多くの場合抗菌薬の塗り薬だけでなく内服も行います。
毛包炎は軽度である場合、多くは特に治療をせずとも自然と治癒します。同じタオルを共有しないことや皮膚は清潔に優しく洗浄する等、日常生活でも注意して周囲への感染を防ぎましょう。なお、症状が進行して、膿があり赤く熱を持っているといったケースでは、皮膚を切開して膿を出す処置をとることがあります。
蜂窩織炎(ほうかしきえん)について
原因菌が皮下に入り込み、真皮深層から皮下組織といった深い部位で起こる急性化膿性炎症を蜂窩織炎と呼びます。
蜂窩織炎の原因となる菌には、黄色ブドウ球菌と化膿レンサ球菌の主に2種類が存在します。患部がまだらに赤く腫れる、虫刺されに似た赤いブツブツが広がる、オレンジの皮に似たゴツゴツしたあばたが出てくるなどが主な症状で、顔や足でよくみられます。強く触ると痛みを感じることや、熱を帯びているケースもあり、蜂窩織炎を放置するとリンパ節の炎症や全身症状(発熱・悪寒・倦怠感・関節痛・頭痛など)を招くこともあります。
なお、人から人への感染はしません。
蜂窩織炎(ほうかしきえん)の治療
蜂窩織炎は、軽症であれば飲み薬で治療を行います。ただし、急速に症状が広がったり、高熱などの全身症状が出ている場合は、抗生剤の静脈内注射・点滴が行われます(必要に応じて、処置が行える医療機関をご紹介します)。さらに、冷たく湿らせたドレッシング剤を患部に当ててクーリングを行い、患部を高い位置に固定(足の場合は下肢挙上)し、むくみと不快感を緩和します。
伝染性膿痂疹(とびひ)について
伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)とは、ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌が原因の皮膚の感染症で、俗名で「とびひ」と呼ばれることもあります。接触により感染し、あっという間に広がる様子が火事の飛び火に似ていることが俗名の由来です。あせもや湿疹、虫刺されなどをひっかいたり、転んでできた傷に二次感染が起きたりすることがとびひを招きます。また、幼児や小児で鼻をよく触る場合、鼻孔の入口には様々な常在菌が存在しているためにそこからとびひが始まるケースがよくみられます。さらに、鼻を触った手であせもや虫刺されを引っかくこともとびひを引き起こします。
伝染性膿痂疹(とびひ)の治療
伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)では、抗菌薬の軟膏を塗り、全体をガーゼで覆うという方法で治療を行います。このガーゼは1日に1~2回交換し、小さな水疱は潰しませんが、大きな水疱は内容液が周囲に付着しないよう注意しながら排出させます。症状がごく軽い場合には塗り薬のみですが、多くの場合は抗菌薬の内服も行います。とびひには強いかゆみを伴うという特徴があるため、抗ヒスタミン薬の内服によってかきむしりを抑え、必要に応じて併発する湿疹の治療を同時に行い、病変の拡大を防ぐことが大切です。
ウイルス性皮膚感染症
単純ヘルペス(口唇ヘルペス・性器ヘルペス)について
2種類のウイルス(HSV-1型もしくはHSV-2型)が皮膚や粘膜に感染することによって引き起こされる急性炎症性皮膚疾患を単純ヘルペスウイルス感染症と言います。このウイルスが皮膚や粘膜に感染すると、発熱や痛み、かゆみを伴う水疱やただれが生じ、初回感染時は免疫がまだできていないため、全身症状が出たり重症化しやすかったりするという特徴があります。
主に口唇や口腔、目などの顔面・上半身で発症し、口唇ヘルペスやヘルペス角膜炎、歯肉口内炎などを引き起こすのはHSV-1型で、主に陰部・下半身で発症し、性器ヘルペスを引き起こすのはHSV-2型です。
単純ヘルペス(口唇ヘルペス・性器ヘルペス)の治療
単純ヘルペスの治療は、主に抗ヘルペスウイルス薬の内服薬・塗り薬を用いてウイルスのDNA複製を阻害することによって行います。
中心となる処方はアシクロビル(ゾビラックス)、バラシクロビル(バルトレックス)、ファムシクロビル(ファムビル)で、ビダラビン(アラセナ-A軟膏)という塗り薬やアシクロビルの眼軟膏(ゾビラックス眼軟膏)を使用するケースもあります(角膜炎がある場合)。重症化しているケースでは、抗ウイルス薬を注射することによって、治療効果がより早く得られることが期待されます。
性器ヘルペスの場合は、保険適用で再発抑制療法(抗ウイルス薬を毎日内服)が行えるようになりました。
水痘(水ぼうそう)について
水ぼうそうは、「水痘・帯状疱疹ウイルス」と呼ばれるヘルペスウイルスが原因の感染症です。水痘・帯状疱疹ウイルスの感染経路は飛沫感染や空気感染、接触感染で、1人が感染するとそのまま家族や幼稚園、保育園で流行するケースがよくみられます。流行時期は冬から春にかけてで、感染から2週間程度の潜伏期間があります。大人の方が発症した場合、お子様よりも重症化しやすい傾向があるため、気になる症状がある場合は当院まで早めにご相談下さい。また、今までに水疱に罹患したことがある方は、体内の神経節に水痘・帯状疱疹ウイルスが潜伏しており、加齢やストレスが原因で体の抵抗力が落ちると再活性化し「帯状疱疹」となることもあります。
水痘(水ぼうそう)の治療
水ぼうそうは多くの場合自然に治癒するため、対症療法を中心に症状を緩和させる治療を行います。症状に合わせて、例えばかゆみが強い場合には抗ヒスタミン剤を、細菌感染による化膿を防止するために抗生物質を、発熱している場合には解熱剤を処方します。
大人の感染で、免疫力の低下等のリスクがある場合は、重症化や合併症を防ぐために抗ウイルス薬を投与します。
帯状疱疹について
 強い痛みを伴う、帯状の赤い発疹が体の神経の分布に沿って生じるウイルス性の疾患を帯状疱疹と言います。症状が左右どちらかに帯のように生じるのが特徴で、これは神経が左右それぞれに分布しているためです。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)が原因で引き起こされ、初回感染時は水ぼうそうになります。水ぼうそうが治癒した後、ウイルスが消えずに神経節に潜んでいるため、加齢や季節の変わり目、過労、体調不良などで体の抵抗力が弱まると「再活性化」することがあります。帯状疱疹とは、その再活性化によって起こる疾患です。
強い痛みを伴う、帯状の赤い発疹が体の神経の分布に沿って生じるウイルス性の疾患を帯状疱疹と言います。症状が左右どちらかに帯のように生じるのが特徴で、これは神経が左右それぞれに分布しているためです。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)が原因で引き起こされ、初回感染時は水ぼうそうになります。水ぼうそうが治癒した後、ウイルスが消えずに神経節に潜んでいるため、加齢や季節の変わり目、過労、体調不良などで体の抵抗力が弱まると「再活性化」することがあります。帯状疱疹とは、その再活性化によって起こる疾患です。
帯状疱疹の治療
帯状疱疹の症状は、年齢ではなく体の抵抗力によって、どの程度重症になるかが決まります。最初は軽症であっても、無理をするとどんどん悪化し、重症になってしまうという特徴があります。帯状疱疹の治療では、できるだけ早く抗ウイルス薬(アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビル、アメナメビル)の内服を行うことが重要です。顔面に症状のある場合は重症化しやすく、入院して抗ウイルス薬(アシクロビル、ビダラビン)を点滴する必要があります。局所にのみ症状が現れている場合、初期は非ステロイド抗炎症薬を、水疱期以降の場合は化膿を防ぐ塗り薬を用いて細菌の二次感染を防ぎます。潰瘍になっている場合には、潰瘍治療薬を塗布します。
帯状疱疹の予防
 帯状疱疹は、症状によって日常生活に支障が出るケースも多く、治療が長引くことも珍しくありません。特に、高齢の方では帯状疱疹後神経痛(PHN)を発症するリスクが高くなるため、帯状疱疹自体を発症しないよう予防することが大切です。50歳以上の方、もしくは帯状疱疹の罹患リスクが高いと考えられる18歳以上の方はどなたでも任意で帯状疱疹予防ワクチンを接種できます。過去に帯状疱疹に罹ったことがある場合でも接種可能です。
帯状疱疹は、症状によって日常生活に支障が出るケースも多く、治療が長引くことも珍しくありません。特に、高齢の方では帯状疱疹後神経痛(PHN)を発症するリスクが高くなるため、帯状疱疹自体を発症しないよう予防することが大切です。50歳以上の方、もしくは帯状疱疹の罹患リスクが高いと考えられる18歳以上の方はどなたでも任意で帯状疱疹予防ワクチンを接種できます。過去に帯状疱疹に罹ったことがある場合でも接種可能です。
なお、令和7年度より、帯状疱疹予防接種が定期接種化される方針が厚生労働省の予防接種基本方針会で示されました。
大田区では、過去に大田区の助成を使用して帯状疱疹予防接種を受けたことが無い、
以下の年齢の方が定期接種の対象となります。
(令和7年4月下旬に対象者へ予診票が郵送される予定です。)
- 60歳以上65歳未満の方の内、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があるとして厚生労働省で定められている方
- 令和8年3月31日時点で、65、70、75、80、85、90、95、100歳以上の方
※100歳以上の方は定期接種開始初年度のみ全員対象
また、50歳以上の方は費用の一部助成があります。(任意接種)
当院でも実施しておりますのでご相談下さい。
>>大田区の助成の詳細はこちらからご覧いただけます。
尋常性疣贅(いぼ)について
ウイルス感染が原因でできた“イボ”を尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)と言います。なお、「イボ」は皮膚の一部が盛り上がったものを指し、原因がウイルス以外であるものも一般的には「イボ」と呼ばれることがあります。
尋常性疣贅(いぼ)の治療
イボは自然に消失するケースもありますが、別の部分に移ることや、大きくなって治癒しにくくなることも少なくありません。
そのため、当院では患者様に定期的に通院して頂いた上で、液体窒素を用いた冷凍凝固療法やヨクイニンという飲み薬の内服、サリチル酸ワセリンなどの軟膏の塗布による治療を行います。
その他、保険診療以外ではレーザー照射やトリクロロ酢酸の塗布、オキサロール軟膏とスピール膏の組み合わせなどの治療もあります。治療はこれらを組み合わせて実施していきます。
市販のイボ治療薬について
市販薬として、イボへの効果が期待できるサリチル酸を含む薬も販売されていますが、ご自身での処置はウイルスを周囲の皮膚に広げてしまい、悪化を招きかねません。正しい治療を実施するために、イボができた場合はお気軽に当院までご相談下さい。
伝染性軟属腫
(水いぼ)について
伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)は、体などの皮膚表面に白く小さなブツブツしたできものができる疾患で、水いぼとも呼ばれています。原因はウイルス感染で、かきこわすと広がりやすく、アトピー性皮膚炎や乾燥肌があると罹患しやすい疾患です。小さなお子様によくみられ、ブツブツは白く小さく、少し光沢があるのが特徴です。
伝染性軟属腫
(水いぼ)の治療
水いぼは自然に消失するケースもありますが、当院では基本的に水いぼを専用のピンセットを用いて1つずつ取り除くという方法で治療を行います。事前に麻酔テープを貼るなどの処置を行い、水いぼを取る際の痛みを軽減しております。
水いぼの数は増えることもあり、また、保育園や幼稚園などの水遊びでは水いぼがあると参加できないケースもあります。当院では、患者様ご本人の状態を考慮した上で保護者の方とご相談し、治療方針を決定いたします。気になることがございましたらお気軽に当院までご相談下さい。
真菌性皮膚感染症
白癬ついて
(水虫・爪水虫等)
白癬とは、カビの一種である「皮膚糸状菌」が原因で起こる皮膚の感染症です。この病気は主に皮膚の表面に現れます。厳密には、白癬のほかに「黄癬」や「渦状癬」といった病気も同じ菌が原因で起こりますが、これらは現在の日本ではほとんど見られません。そのため、皮膚糸状菌が原因の病気をまとめて「白癬」と呼ばれています。
白癬の中でも特によくみられるのは足に生じる足白癬(水虫)です。その他、股に生じる股部白癬(インキンタムシ)や、髪に白癬菌が感染した頭部白癬(シラクモ)、手に感染した手白癬や爪に感染した爪白癬(爪水虫)などがあります。また、体の股以外の部分に白癬が生じた場合は体部白癬といい、銭型をしているためにゼニタムシとも呼ばれています。また、ごく稀に、深在性白癬と呼ばれる、白癬菌が皮膚の表面より内側、もしくはそれより深部に入り込んでしまうケースが存在します。
白癬の治療
白癬の治療では、患者様それぞれの症状が現れた部位や病状、基礎疾患や合併症を考慮して内服薬や塗り薬を処方します。足白癬や体部白癬では、ほとんどの場合感染は皮膚の角層のみで起こっているため、抗真菌作用のある薬をしっかり塗布することで改善が見込めます。ただし、足白癬であっても角層が分厚くなっている病型である角質増殖型や、頭部白癬や爪白癬では、塗り薬では十分な効果が得られないため、内服薬を用いて治療を行います。
体部白癬や股部白癬は、薬の塗布を2か月以上続ければ完治が見込めます。しかし足白癬の場合は両足の指の間から足の裏全体まで、一見症状が無いように見える部分にもしっかりと、「最低12週間毎日薬の塗布」を続けないと治癒しません。薬の塗布開始から2週間程度で症状が緩和してきますが、その場合でも角質の中では菌が生きています。そのため、治療を中断してしまうと症状が悪化するというケースも珍しくありません。
白癬には民間療法も多く存在しますが、医学的に疑問のあるものがほとんどで、お勧めできることはないため、治療が必要な場合は当院までご相談下さい。また、2~4%程度の頻度で治療薬のかぶれが発生しますので、専門医による治療が必要です。